こんにちは~!
段々と温かくなってきましたねぇ😊春を感じます!
先日は3月3日、ひな祭りでしたね!
ひな祭りは「桃の節句」、「弥生の節句」とも呼ばれ、女の子の成長と幸せを願うものなんですね。
皆さんのお家では雛人形は飾ってますか?
私は末っ子でお姉ちゃんはいますが、歳が離れているため、お雛様が家に飾られているところを見たことがありません🙄
妹がいたら、飾ってたのかなぁ🤔?
こういう行事になるといつも思いますが、行事の由来とか意味とかってなんとなくしかわかってないですねぇ。
でも両親やおじぃちゃん、おばぁちゃん世代の方って、こういうの詳しい人多いですよね!
携帯電話やインターネットも無い時代に色々知っててすごいと思います。
おばあちゃんの知恵袋、長い物には巻かれよ、とは良くいったものです😆
◇ひな祭りの由来
元々、ひな祭りというものは中国から平安期頃に日本に伝わったものなんですね!
中国の五節句のうちの一つ「上巳の節句」で「忌日」という日に「けがれを祓う厄払いのため、水辺で身体を清めること」が元のようで、それが日本に伝わり、「流しびな」という土や紙の人形にけがれを移して水に流す行事と変わりました。←こうなると「上巳の節句」と「忌日」がわからんですが、それはまた後日・・・・(/ω\)
京都かどこかに「人形祓い」という魔除けがあった気がしますね!それに似た感じかなぁ🙄
「流しびな」が貴族の子供の間で「ひいな遊び」という、お人形遊びに変わったとか。
それが江戸時代になると、武家や貴族の間でひな人形を段飾りにして飾り、お祝いをするようになったそうです。
一般家庭で飾るようになったのは、明治以降だそうです。
結構、昔からあるんですね。
①中国の五節句のうちの一つ「上巳の節句」忌日に行われる「けがれ祓い」
↓
②日本の平安期に「流しびな」として伝わる。
↓
③貴族の間で「ひな遊び」という人形遊びに変わる
↓
④江戸時代に「ひな人形を段にして飾る」
↓
⑤明治時代に一般家庭でも飾るようになる。
こんな感じなんですね😄何やら伝言ゲームのようだ🤔
ひな人形にけがれや厄を移して身代わりになってもらうという意味もあるそうです。
他にも諸説あるようですが。
長く飾っておくと婚期が遅れるなんて話もありますよね。
深く調べるとまだまだありそうですが、今回はこの辺にしておきましょうかねwww
普段は軽く流してしまいそうなものでも、調べると奥深いですね!
今後も気になったことは調べて記載していきたいと思います。
文章力やまとめる力をつけて、わかりやすく伝えられるようになりたいですね。
これからも頑張りますのでよろしくお願いします。
では、本日はこの辺で。
またね~(=゚ω゚)ノ
※ブログはなるべく毎日更新していきます!私自身や皆さんのモチベーションが上がるように努力していきますので、お気に入り登録やスマホのトップ画面に登録してもらえると嬉しいです(≧▽≦)
よろしくお願いしますm(_ _)m
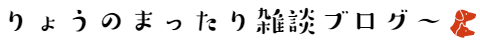

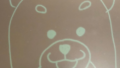
コメント